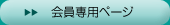少年法の適用年齢引き下げに改めて強く反対する会長声明
1 当会は,2015(平成27)年6月30日付けで,「少年法の適用年齢引下げに反対する会長声明」を発出し,少年法の適用年齢の引下げに強く反対することを表明したが,ここにあらためて反対の意思を表明する。
2 現在,法制審議会少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会においては,少年法の適用対象年齢を18歳未満とすることの是非等についての議論がなされている。
上記法制審議会においては,少年法の適用対象年齢を18歳未満に引き下げるべき理由として,①選挙権年齢や民法上の成人年齢が18歳となることから,少年法の適用対象年齢も18歳未満に統一することが国民にわかりやすいこと。②民法の行為能力及び親権に服する年齢が18歳に引き下がり,「保護者」の監護に服さないことになる者に対して保護処分を課すことはできないから,少年法上の「少年」の年齢についても,もはや20歳未満とする現行法は維持できない。③年齢を引き下げたとしても,少年法の対象から外れる18歳及び19歳の若年者が起訴猶予となった場合には,家庭裁判所に送致して少年法と同様の処分を実施するという「若年者に対する新たな処分」で対応すれば問題ないことなどが挙げられている。
しかしながら,上記の理由はいずれも少年法の適用対象年齢を引き下げる理由にはなりえない。
3 まず,上記法制審議会は,①国法を統一する方が国民にわかりやすいと説明するが,これは少年法の適用年齢を引き下げる根拠にはならない。
民法の成年年齢の引下げがなされたが,それは,18歳及び19歳の若年者は成長の過程にある未熟な存在であることを前提にした上で,主に経済取引を前提に行為能力を認め,ひいては,積極的な意欲を有する者の社会参加を促す,という目的からである。
一方で,少年法の目的は,「少年の健全な育成を期し,非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに,少年の刑事事件について特別の措置を講ずること」(少年法1条)であり,民法の成年年齢引き下げの論拠をそのまま少年法に及ぼすとすると,少年法の目的を阻害しかねない。少年法の適用年齢は,対象者の立ち直りを図るための援助を行う必要性や再犯の防止効果を含む刑事政策的な観点から議論されるべき問題であり,民法で成年年齢が引き下げられるから少年法の適用年齢を引き下げようとする論法はあまりに乱暴である。
また,民法の成人年齢を18歳とすることから,少年法の適用年齢を18歳にしなければならないわけではない。適用年齢は,それぞれの法律の趣旨に従って適用年齢を考慮することが重要であり,飲酒,喫煙,ギャンブルなどに関する各法律については適用年齢が引き続き20歳以上とされていることからしても,上記法制審議会が掲げる国法の統一といった論拠は当てはまらない。
4 次に,法制審議会は,②「保護者」の監護に服さないことになる者に対して保護処分を課すことはできない,と述べるが,これも論拠とならない。少年法には 「保護者」という概念が存在し,これには親権者が含まれるが,少年法の保護者は,法律上の親権者に限られるものではなく,少年を事実上監護する者も含まれるとするのが一般的な解釈である。すなわち,対象者が親権に服さなくなったとしても,裁判所が「保護者」の認定をすることは可能であって,少年法の適用は十分可能である。したがって,「保護者」の解釈の観点からも,少年法の適用対象と民法の未成年者の範囲を連動させる必然性は全くない。
5 18歳及び19歳の若年者が少年法上の処遇から除外されると,現在の少年被疑者全体のうち約4割もの少年が少年司法手続から排除されることになる。そして,それらの事件の多くは,検察官による不起訴処分や略式命令による罰金刑をもって手続が終了することになりかねない。
そうなれば,少年法の適用年齢引下げによって成人とされた18歳及び19歳の若年者が,立ち直りに向けた十分な処遇を受けられないまま放置されることとなり,その更生が阻害されてしまうおそれも否定できないのである。
そこで、法制審議会では,少年法適用対象年齢引下げによって少年法上の処遇が受けられなくなる18歳及び19歳の若年者に対しては,代替手段として,起訴猶予となった者を家庭裁判所へ送致し,家庭裁判所調査官の調査や,少年鑑別所での鑑別を経て,保護観察処分等の新たな処分の要否を判断することが検討されており,この新たな措置が法制審議会の少年法適用年齢引き下げの論拠となっている(上記③)。
しかし,そもそも,適用年齢の引下げの可能性を前提に,現在の少年法に基づく処遇に代わる措置を検討すること自体が不合理である。
また,かかる新たな処分は,健全育成という少年法と同様の理念に基づいて少年の資質面・環境面の問題点を明らかにするものではない。新たな処分を前提とする調査や鑑別は,犯罪に対する非難と再犯防止のための調査・鑑別に過ぎないのであるから,教育として個別の処遇をしている現行少年法制度の代替制度には到底なりえない。
さらに言えば,法制審議会は国法の統一を掲げながらも18歳及び19歳の若年者に新たな措置を検討している。これは現行の少年法が18歳及び19歳の少年に対しての処遇として十分に機能しており無視できないからに他ならない。現行の少年法の処遇に代わる新たな措置を検討すること自体が無駄な議論である。
6 以上のとおり,少年法の適用年齢を引き下げる必要性はなく,むしろその弊害が極めて大きい。
よって,当会は,少年法の適用年齢を18歳未満に引き下げることについて,改めて強く反対する。
2019年(令和元年)6月12日
沖縄弁護士会
会 長 赤 嶺 真 也