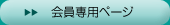少年法の適用年齢引下げに反対する会長声明
自由民主党は、選挙権年齢を18歳以上に引き下げる改正公職選挙法の附則第11条で「少年法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする」とされていることを受け、「成年年齢に関する特命委員会」を設置し、少年法の適用年齢を現行の20歳未満から引き下げることについて議論を開始した。同委員会では、少年法の適用年齢の引下げを求める意見が相次いだとの報道もなされている。
しかしながら、以下のとおり、少年法の適用年齢を引き下げるべきではない。
1 現行の少年司法が有効に機能していること
(1)少年犯罪が減少していること
少年は、心身の発達が十分でなく、少年を取り巻く環境の影響を受けやすい反面、可塑性に富んでいるとされている。そのため、少年に対しては成人の刑事事件と異なり、性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うことによって、少年の健全育成を図り、再犯を防止するというのが少年法の目的である。
かかる立法趣旨を受け、少年法は、全ての事件を家庭裁判所に送致させ(全件送致主義)、家庭裁判所調査官及び少年鑑別所において、少年、保護者等の行状、経歴、素質、環境等について、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識を活用した調査を行っている(科学主義)。そして、その調査結果をふまえて、環境調整や教育的働きかけが行われ、審判において、少年の立ち直りのための最善の処遇が決められている。このような保護・教育的な処遇こそ、少年の更生及び再犯防止に資するのである。
そして、警察庁の発表によると、刑法犯少年の検挙人員は、2005(平成17)年に12万3715人であったのが、以後減少し続け、2014(平成26)年は4万8361人となり、この10年間で約6割減少して戦後最少を更新した。また、殺人、強盗、放火、強姦等といういわゆる凶悪犯罪についても、2005年の検挙人員は1441人であったが、2014年にはその約2分の1である703人にまで減少した。いずれも少年人口の減少率を遙かに上回って減少しており、少年犯罪が増加しているとか凶悪化しているという事実はない。むしろ、上記データが示すとおり、少年犯罪は減少しており、適用年齢を引き下げることを基礎づける立法事実は存在しない。
(2)少年の再非行率等が成人よりも低いこと
加えて、平成26年版犯罪白書によると、2013(平成25)年の一般刑法犯検挙人員中の再犯者率は46.7パーセントであるのに対し、同じく2013(平成25)年の少年の一般刑法犯検挙人員中の再非行少年率は34.3パーセントであり、少年の方が10ポイント以上低い。同じく平成26年版犯罪白書によれば、2009(平成21)年の出所受刑者について出所年を含む2年間における再入率が20.0パーセントであるのに対し、2009(平成21)年に少年院を出院した者で2年間に再入院した者の比率は11.9パーセントである。少年法上審判ができる対象年齢の制限があるため単純な比較はできないにしても、出院後2年間に再入院した少年の方の割合の方が、出所後2年間に再入所した受刑者の割合よりもかなり低くなっている。
これらのように、再非行に及ぶ少年の割合及び再度少年院に入院した少年の割合は、成人の再犯者率や再入率に比べても低くなっているのである。つまり、保護・教育的な観点を重視する現行の少年司法は有効に機能しているのであり、少年法の適用年齢を引き下げるべき理由はない。
2 適用年齢引下げにより再犯のリスクを高めること
少年法の適用年齢を18歳未満に引き下げてしまうと、18歳、19歳の者が比較的軽微な犯罪を行った場合、その多くが、起訴猶予や罰金、執行猶予となり、犯罪の背景、要因となった資質や環境上の問題点等に関する調査・分析や立ち直りのための教育が施されないまま社会に戻されることとなる。これでは、更生と立ち直りにはつながらない。このように家庭裁判所の少年事件の対象外とされてしまう少年は、現在、家庭裁判所が対応している少年の実に約4割にもなるところ、少年法の適用年齢を18歳未満に引き下げてしまうことは、多くの少年の教育の機会を奪うことになり、再犯の危険性が増すことになってしまう。
3 少年法が決して甘くないこと
現行の少年法においても、16歳以上の少年による一定の重大事件については、検察官送致(逆送)が原則である旨が規定されており、家庭裁判所が刑事処分相当と判断した事件については、検察官に送致し刑事裁判に付することとなっている。実際に、重大事件を犯した少年の多くが公開法廷における刑事裁判を受け、裁判員裁判の対象にもなっている。このように、少年法の適用年齢を現行のまま維持したとしても、成人と同様の刑事裁判を受けることがありうるのである。しかも、少年が刑事裁判を受けた場合の刑罰についても、2014(平成26)年6月に厳罰化の方向で改正が行われたばかりである。また、成人では比較的軽微とされ、実刑にならない事件であっても、少年であれば少年院送致になる場合があり、少年法の方が成人と比して厳しい処分となることもある。
このようなことからして、少年法が18歳以上の少年を過剰に保護しているわけではなく、少年法は決して甘くないのである。
4 適用年齢は法律ごとに個別に決められるべきであること
法律の適用年齢は、立法趣旨やそれぞれの制度の目的に応じて個別具体的に決められるべきものである。例えば、民法では法律行為の行為能力を持つのは20歳とされている一方、養子縁組能力や遺言能力を15歳で認めている。また、喫煙や飲酒は20歳から認められているが、パチンコ店への入店は18歳から認められている。しかるに、少年法と公職選挙法は、立法趣旨も制度の目的も異なるのであるから、それぞれの適用年齢が異なったとしても何ら不合理でなく、選挙権年齢が18歳以上になったとしても、少年法の適用年齢をそれに連動させる必要は全くない。
5 結論
以上のとおり、少年法の適用年齢の引下げは、それを基礎づける立法事実が存在しないばかりか、有効に機能している少年司法を覆して再犯のリスクを高めてしまうものである。
よって、当会は、少年法の適用年齢の引下げに強く反対する。
2015(平成27)年6月30日
沖 縄 弁 護 士 会
会 長 阿波連 光