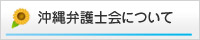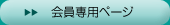同性カップルの婚姻を可能とする法整備を求める会長声明
1 同性カップルの婚姻を認めていない民法及び戸籍法の規定(以下「本件諸規定」という。)の合憲性が争われた「結婚の自
由をすべての人に」訴訟において、2025(令和7)年3月25日までに、札幌、東京、福岡、名古屋及び大阪の5つの高
裁で、いずれも違憲判決が言い渡された。これらの訴訟は、現在、最高裁判所に係属しているが、国会は、速やかに民法や戸
籍法など関係法令を改正し、同性婚を可能にする法制度を整備するべきである。その必要性は、以下のとおり明確である。
第一に、上記5つの高裁判決が判断しているとおり、本件諸規定は、合理的理由なく性的指向によって法律婚制度を利用で
きない区別を生じさせている点において、憲法14条1項に違反する。また、婚姻の自由を定めた憲法24条1項に違反して
おり(札幌高裁判決)、婚姻に関する法律は個人の尊厳に立脚して制定されるべき旨を定めた同条2項にも違反している(上記す
べての高裁判決)。このように、本件諸規定が憲法違反であるとの司法判断が積み重ねられている現在、もはや現行法が憲法
14条や24条に適合していないことは明らかであり、国会が何ら法制度を改正しないという姿勢は、立憲主義の趣旨に悖る
というべきである。
第二に、同性婚を法的に認めることは、憲法13条の個人の尊厳を保障することに直結する。婚姻は法律上の契約関係であ
ると同時に、社会から公的に承認された家族になることを意味する。同性カップルにも婚姻の扉を開くことは、全ての人が等
しくかけがえのない存在として尊重される社会を実現するための象徴的かつ実質的な一歩である。
第三に、近年、日本社会における同性婚への支持と理解は飛躍的に高まっている。各種報道機関の全国調査では、「同性婚
を法的に認めるべきだ」とする意見が軒並み過半数を占め、近年では6~7割程度に達している。具体的には、読売新聞の調
査(2023(令和5)年)で賛成66%・反対24%、朝日新聞の調査(同年)では賛成72%・反対18%という結果が出
ており、他の主要メディアの調査においても賛成が概ね6割台から7割前後にのぼる傾向が確認されている。これらの統計か
らも明らかなとおり、同性婚の法制化は国民的多数の要請となっており、もはや同性婚を認める立法措置を猶予する合理的理
由は見当たらないというべきである。
第四に、日本における同性婚の法制化の遅れは、国際的な人権保障の流れからみても際立っている。現在、欧米諸国を中心
に世界各国で同性婚の法制化が進んでおり、主要先進国では日本だけが同性婚を認めていない状況にある。2025(令和7)
年1月時点で、世界39の国・地域で同性婚が可能となっている。欧州ではオランダ(2001(平成13)年)を皮切りに
多数の国が婚姻の平等を実現し、カナダ(2005(同17)年法改正)、米国(2015(同27)年連邦最高裁判決)、オ
ーストラリア(2017(同19)年法改正)などの英語圏諸国も、すでに同性婚を認めている。アジアにおいても2019
(令和元)年に台湾が初めて同性婚法を施行し、2023(令和5)年にはネパール最高裁が事実上の合法化に動くなど、従来消
極的とされた国・地域においても、変化の兆しがみられる。政府・国会はかかる国際的潮流を真摯に受け止める必要がある。
2 本件諸規定の違憲性を解消する方法として、同性カップルを公的に承認するパートナーシップ制度を創設する方法が主張さ
れることがある。しかし、現在のパートナーシップ制度は法律上の権利が保障される婚姻とは大きな隔たりがあるうえに、大
阪高裁判決が同性カップルについてのみ婚姻とは別の制度を設けることは新たな差別を生み出すとの危惧が拭えないと指摘し
ているとおり、婚姻制度そのものを保障しなければ法の下の平等は実現しないと言うべきである。法改正の遅れによって同性
婚が認められていないことにより、同性カップルは法的・社会的な不利益(配偶者としての相続権がない、税制上の差別、医
療や公的手続での家族不承認など)を日常的に受けており、また法律上他人とされることによって受ける心理的苦痛や社会的
な疎外感は、同性カップルの尊厳を深く傷つけ、その人格的利益を損なわせている。このような同性カップルの受ける苦痛は
、法改正がなされれば直ちに解消し得るものであり、一刻も早い救済が求められる。
3 これまで、当会は、憲法に基づき性の多様性が全面的に尊重される社会を目指して性的少数者のための取り組みを進めてい
くレインボー宣言の表明(2019(平成31)年3月20日付け)、性的少数者に対するあらゆる差別に反対する会長声明(20
23(令和5)年6月29日付け)及び同性婚を認めていない民法及び戸籍法を違憲と判断した札幌地裁判決を受けての会長談話
(2021(令和3)年3月30日付け)を発出してきた。同性婚を法的に認めることは、憲法が予定する国民の権利保障を具体
化する作業であり、法の下の平等と多様性を推進する意義を有するもので、もはや立法措置を躊躇する合理的な理由はない。
よって、当会は、改めて国会と政府に対し、速やかに民法や戸籍法など関係法令を改正して同性婚を制度化するよう求め
る。
2025年(令和7年)9月29日
沖縄弁護士会
会長 古 堅 豊