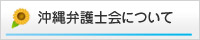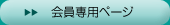子どもの権利条約に基づく子どもの権利保障の推進を求める会長声明
1 子どもに関する施策及び現状
2024年は、子どもの権利条約批准から30年という記念の年です。
子どもの権利条約は、①差別の禁止、②子どもの最善の利益、③生きる権利・育つ権利、④意見を聴かれる権利(意見表
明権)という4つの一般原則を指針としながら、それまで「保護の客体」として扱われていた子どもを、「権利の主体」と
みて、子どもの権利の実現を求めるものです。
2023年4月、憲法及び子どもの権利条約に則り、こども施策に関する基本理念を定めたこども基本法が施行され、同
年末には国の施策の基本方針を定めたこども大綱が決定されました。また、同法成立後に改訂された生徒指導提要や閣議決
定された教育振興基本計画においても、不十分ではあるものの子どもの権利に関する記載がなされ、批准から30年経過し
、ようやく子どもの権利が保障される社会への一歩を踏み出しました。
沖縄県においても、2022年4月1日から、「沖縄県子どもの権利を尊重し虐待から守る社会づくり条例(以下、「沖
縄県条例」といいます。)」が施行されています。沖縄県条例には、子どもは、子どもの権利が保障され、個人としての尊
厳が重んぜられるとともに、 その最善の利益が考慮されなければならないという基本理念が定められています(沖縄県条例
第4条)。また、2024年6月には、こども基本法第10条に基づく都道府県こども計画として、「沖縄県こども計画(
仮称)」の策定を目指して沖縄県こども・子育て会議が設置され、現在、同計画策定に向けて検討が進められています。
しかしながら、児童虐待、いじめ、不登校、子どもの自殺など子どもの問題は増加しています。沖縄県における2021年
度の児童相談所の児童虐待相談対応件数は過去最多の2509件、いじめ認知件数は1万4139件、小中学校の不登校児童
生徒数は5762人で、いずれも増加傾向にあります。また、沖縄県の2023年の子どもの貧困率は20.2%と依然とし
て高い数値であり、生きる権利や安心できる環境で過ごす権利、教育を受ける権利を奪われている子どもたちが少なくない状
況です。
このように、今なお、家庭や学校において、子どもたちの権利が十分に保障されていない現状があります。
2 子どもの権利について
⑴ 子どもは権利の主体であること
子どもは、自由かつ独立の人格を持った権利の主体です。子どもを未熟な保護の客体として扱うのではなく、大人と同じ
対等な価値を持つ一人の人間として尊重しなければなりません。子どもは、大人と共に社会を構成するパートナーであり、
大人は決して子どもの支配者ではありません。このような子ども観を浸透させ、子どもに関わるあらゆることについて子ど
もの権利を意識し、子どもの権利を基盤にして子どもたちのことを考える必要があります。
⑵ 意見表明権
子どもには意見表明権があります(子どもの権利条約12条)。
子どもは自分に影響を及ぼす全ての事項について自由に自己の意見を表明する権利があり、子どもの意見は、子どもの年
齢や成熟度に従って相応に考慮されなければなりません。さらに、子どものことを決め、実行する際には、子どもの最善の
利益を考えなければならないところ(子どもの権利条約3条)、子どもの最善の利益を評価する際には、子どもに影響を与
えるすべての事柄について子どもが自由に自己の意見を表明でき、かつ表明した意見が正当に重視されるという形で子ども
の権利が尊重されていなければなりません。子どもの意見表明権を保障する意識、文化、制度を社会に根付かせることが必
要です。
3 子どもの権利保障のために必要な施策
⑴ 啓発活動
子どもの権利を十分に保障するためには、その義務を負う大人が子どもの権利を学び、理解しなければなりません。子ど
もに関わる職業にある者はもちろんのこと、広く大人たち、そして権利を享受する子どもたちも、子どもの権利に関する理
解を深めなければなりません。沖縄県条例においても、子どもの権利の重要性に関する理解を深めることを沖縄県民の責務
とする共に(沖縄県条例6条)、沖縄県は、基本理念に関する県民の理解を深めるため、必要な広報その他の啓発活動を行
うこととしています(沖縄県条例10条)。
⑵ 権利救済機関の設置
子どもの権利を実効的に保障するためには、子どもの権利が侵害されないよう監視し、侵害された場合に救済することが
不可欠であり、子どもに関わる制度が子どもの権利保障のために機能しているかを監督し、権利侵害された場合に救済する
ための権利救済機関が必要です。現在検討がされている沖縄県こども計画(仮称)においても、子どもの権利救済機関設置
の方針が含まれており、今後の具体化が望まれるところです。
4 まとめ
以上より、子どもの権利が十分に保障される社会を作るために、国、沖縄県、沖縄県内の各市町村に対し、より一層子ども
の権利条約に基づく子どもの権利保障を推進していくこと、特に、社会全体で子どもの権利に関する理解を深めるための子ど
もの権利の普及啓発活動を行うこと、各々の役割を踏まえ、連携して子どものための権利救済機関を設置することを強く求め
ます。
当会も子どもの権利の普及啓発や子どもの権利相談、家事事件における子どもの手続代理人、少年事件における付添人など
の活動を通じて、子どもの権利が保障される社会の実現に向けて尽力していきます。
2024年(令和6年)12月26日
沖縄弁護士会
会長 野 崎 聖 子