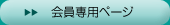死刑制度の廃止を求める決議
生命は尊貴である。一人の生命は、全地球よりも重い。
最高裁判所昭和23年3月12日大法廷判決(刑集2巻3号191頁)の有名なフレーズである。同最判は、「死刑は、まさにあらゆる刑罰のうちで最も冷厳な刑罰であり、またまことにやむを得ざるに出ずる窮極の刑罰である。それは言うまでもなく、尊厳な人間存在の根元である生命そのものを永遠に奪い去るものだからである」ことを前提にした上で、「(新)憲法は、現代多数の文化国家におけると同様に、刑罰として死刑の存置を想定し、これを是認したものと解すべきである」などとして、死刑を定めた刑法の規定は違憲ではないと判断した。
当時、全面的死刑廃止国は世界でわずか8か国であった。それから70年以上経過した現在(2020年末)、法律上・事実上の死刑廃止国は144か国にまで達し、死刑存置国は55か国(そのうち昨年死刑を執行したのは18か国)に過ぎない(アムネスティーインターナショナルの情報による。)。時代は大きく変わった。
しかし、昭和23年の上記最判は、今なお判例として生き続け、我が国では、毎年のように死刑執行が繰り返されている。我々は、今こそ、制度論・政策論として死刑制度の是非を考えてみるべきである。
政府が死刑存置の根拠として重視する世論調査結果を仔細に見てみると、条件次第で死刑廃止に賛成する層が国民の半数近くに上ることが明らかになる。死刑制度固有の犯罪抑止力の存在を証明することはできない。被害者遺族が死刑を求めるのも無理はないが、処罰感情を主たる根拠として「尊厳な人間存在の根元である生命そのものを永遠に奪い去る」(上記最判)死刑制度を正当化することはできない。他方で、誤判による死刑執行は絶対に避けなければならないが、誤判は不可避である。誤判による死刑執行を避けるためには死刑を廃止するほかない。
死刑廃止の国際的潮流が確固たるものとなっている今、我が国においても、多くの国民の理解を得るよう努力をした上で、死刑制度を廃止すべき時期に来ていると言うべきである。
当会は、基本的人権の擁護と社会正義の実現という使命を担う弁護士(弁護士法1条)によって構成される法律家団体の立場において、以下のとおり決議する。
第1 決議の趣旨
当会は、政府及び国会に対し、
1 死刑の代替刑を導入するとともに、犯罪被害者支援の抜本的拡充をした上で、死刑制度を廃止すること
2 死刑制度廃止までの間、死刑の執行を停止すること
を求める。
第2 決議の理由
1 死刑制度に関する弁護士会の取組み
弁護士が、国家権力による人権の侵害に対し、これを批判し、これに立ち向かうことはもとより、弁護士が、司法制度の
健全な発展のため、現行制度に対する批判や改善・改革の提言を行うことも、その重要な使命である。しかしながら、現行
制度に関する批判・提言等により我が国の司法制度を発展させるという政策的課題について、個々の弁護士の力に多くを期
待することは現実的ではない。弁護士によって構成される法律家団体である弁護士会こそが、基本的人権の擁護と社会正義
の実現の観点から、立法や制度改革に関する提言を積極的に行い、司法制度の発展という使命を果たしていくことが求めら
れる。
とりわけ刑事司法の分野においては、構造的に、国家権力と被疑者・被告人らが厳しく対立しており、被疑者らの人権が
危険にさらされる場面が常に生じ得る。その際に被疑者らの人権を守るべき立場にあるのが弁護士(弁護人)である。国家
機関から独立した弁護士会が、被疑者・被告人らの基本的人権を擁護する観点から意見を述べることの重要性は大きい。我
が国の死刑制度に問題があるのであれば、その廃止を含む制度改革の意見を表明することは弁護士会の責務である。
日本弁護士連合会は、2016(平成28)年、第59回人権擁護大会において、2020(令和2)年までに死刑制度の廃止を目
指すべきであることを明らかにした「死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言」を採択した。この宣言を
実現するため、同連合会は、2017(平成29)年に「死刑廃止及び関連する刑罰制度改革実現本部」を設置し、2019(令和
元)年には「死刑制度の廃止並びにこれに伴う代替刑の導入及び減刑手続制度の創設に関する基本方針」を取りまとめるな
ど、死刑制度の廃止に向けた活動を継続している。
各地の弁護士会は、これに呼応するように、2016(平成28)年以降、13の弁護士会(滋賀、宮崎県、札幌、大阪、島根
県、埼玉、福岡県、東京、広島、愛知県、仙台、神奈川県、東京第二)と1つの弁護士会連合会(中国地方)において、死
刑制度の廃止を求める決議がなされている。
当会では、2012年10月、死刑廃止問題検討PTが発足した。これを機に、死刑問題に関する会としての取組みが本格的
にスタートした。その後、海外の死刑制度、死刑事件弁護、無期懲役刑の実情等に関する勉強会、死刑関連問題をテーマ
にした映画上映会、死刑制度廃止・存置双方の立場からのパネルディスカッション、冤罪をテーマにしたシンポジウム、犯
罪被害者遺族による講演会等を開催してきた。
このような活動の中で、2015年12月、死刑執行に抗議する会長声明を初めて発出し、以後、2018年12月27日の死刑執行
まで、死刑執行がある度に合計10回にわたり同様の会長声明を出してきた。
2 死刑廃止に向かう国際的潮流
死刑制度に関する世界の動向を見てみよう。
1940年代、全面的死刑廃止国はわずか8か国であった。1970年代から徐々に増え始め、1995年には59か国にまで増え
た。それでも死刑存置国が多数を占めていた。その後も増加の一途を辿り、2020年末現在、全面的死刑廃止国は108か国に
まで増加し、これに、軍事犯罪等を除く通常の犯罪について死刑を廃止している国8か国、10年以上死刑執行をしていない
事実上の廃止国28か国を加えた法律上・事実上の死刑廃止国は、合計144か国にも上る。これに対し、死刑存置国は55か国
であり、そのうち2020年に死刑を執行したのはわずか18か国に過ぎない。1990年代半ばから、急速に死刑廃止国が増えて
いることが分かる(以上、アムネスティーインターナショナルの情報による。)。
次に、先進国グループの集まりであるOECD(経済協力開発機構)加盟国37か国(2020年)に限って見ると、死刑を
存置しているのは、我が国、米国、韓国のみである。このうち、韓国は10年以上死刑を執行していない事実上の廃止国で
ある。米国では、最近、死刑を廃止する州が毎年のように増え続けている。2021年3月の時点で、50州中23州が死刑を廃
止し、3州が死刑執行を停止しており、死刑廃止・停止州が過半数を超えるに至った。死刑執行をコンスタントに続ける我
が国は、OECD加盟国の中でも異例な存在であることが分かる。
更に、国連の動きについて見ると、2020年、国連総会は、死刑廃止を視野に入れた死刑執行停止を求める決議案を賛成
123か国、反対38か国(日本を含む)、棄権24か国の圧倒的多数で採択した。同様の決議は今回で8度目であり、賛成の国
は着実に増えている。
1948年に世界人権宣言が国連総会で採択された当時、死刑存置国が圧倒的多数を占めた国際社会は、今やその大半が死
刑を法律上・事実上廃止するに至っている。死刑廃止はまさに国際的潮流となっている。
人間の尊厳及び基本的人権の尊重の重要性に対する認識の深化、その結果として、人権享有の前提となる生命(権)の
絶対不可侵性という理念・価値観の普遍化が、この潮流の背景になっているものと考えられる。
3 我が国の現状と世論
我が国は、世界が死刑廃止に向かう中で、国連の自由権規約委員会・拷問禁止委員会による勧告のほか、人権理事会の普
遍的定期的審査において、死刑執行を停止し、死刑廃止を前向きに検討するべきである等との勧告を繰り返し受けながら
も、死刑制度を維持し、死刑執行をコンスタントに続けている。
政府は、死刑の存廃は各国独自に決定すべきものであることを前提とした上、国民世論の多数が極めて悪質、凶悪な犯罪
については死刑もやむを得ないと考えており、凶悪犯罪がいまだ後を絶たない状況等に鑑みると死刑を廃止することは適当
ではないとしている。
ここで、政府が死刑存置の拠り所とする最新の世論調査(2019年11月)の結果を見てみよう。
「死刑は廃止すべきである」(①)…9.0%
「死刑もやむを得ない」(②) …80.8%
となっている。一見、政府の立場を裏付けているように思える。
しかし、②の回答者は、将来の死刑廃止について、
「状況が変われば、将来的には、死刑を廃止してもよい」(③)…39.9%
「将来も死刑を廃止しない」(④)…54.4%
と回答している。「将来の」死刑廃止の当否に対する態度という基準で分けてみると、
廃止賛成(①+②×③)…41.3%
廃止反対(②×④)…44.0%
となる。賛否は拮抗している。
後述のとおり、我々は、即時無条件で死刑を廃止すべきであると言っているのではない。死刑の代替刑の導入、被害者支
援の抜本的拡充と併せて、死刑を廃止すべきであると主張している。我々の議論は、上記世論調査で言うところの「将来
の」死刑廃止である。
世論調査の結果から、相対的には死刑存置の意見が多いことは見て取れる。しかし、強固な廃止論者と強固な存置論者の
中間に位置する人たちは、どちらかの立場に固執しているわけではなさそうである。死刑存置に親和的な人でも、廃止の条
件次第では、廃止に賛成する可能性が十分にあるものと言える。
「死刑もやむを得ない」と回答する人が約8割を占める我が国の世論状況を前提にしても、代替刑の導入等の施策と併せ
て死刑を廃止することは十分可能な状況にあると評価すべきである。
4 死刑制度を支える論拠
死刑制度を支える主要な論拠について見てみよう。
⑴ 死刑の犯罪抑止力
刑罰一般の犯罪抑止力とは別に、死刑固有の犯罪抑止力があるかについては古くから議論されている。
国連において、死刑廃止国と死刑存置国の犯罪動向の比較、死刑廃止国の廃止前後の犯罪動向の比較などの科学的・統
計的調査を行った結果、死刑に他の刑罰とは異なる特別な犯罪抑止力があるとの実証はできないと結論付けられている。
他にも様々な研究がなされているが、死刑固有の犯罪抑止力を証明できないことについては、専門家の間でほぼ共通認識
になっている。
死刑が生命権を国家の名において強制的に剥奪する究極の刑罰であることに鑑みると、あるかどうか分からない死刑の
犯罪抑止力を死刑存置の根拠とすることはできない。
⑵ 遺族の処罰感情
命を奪われた被害者、被害者を突然失った遺族が、加害者に対し、厳罰を望む、法定刑に死刑があれば死刑を望むとい
うことは、十分理解できる。実際、殺人事件の裁判において、被害者遺族が被告人に対し死刑を求めることはよくある。
しかし、判決で死刑が言い渡されるかどうかは、犯行に至る経緯・動機、犯行態様、犯行結果等の犯罪事実自体に関す
る情状(特に、死亡被害者の数)によって決まってくる。遺族が死刑を望めば死刑になる、逆に遺族が死刑を望まなけれ
ば死刑にならない、ということはない。
そこで、死刑廃止を支持する立場からは、被害者遺族の処罰感情が死刑か無期かの判断の場面で重要なファクターにな
らない以上、これを死刑制度存置の主たる根拠とすることは合理的ではないという反論がなされている。
5 誤判・冤罪
死刑廃止論の思想的・理念的理由は、人間の尊厳及び基本的人権の尊重にあるが、実際的な理由としては、誤判・冤罪
(以下、冤罪を含む広い意味で「誤判」を使用する。)の問題が指摘されている。
死刑が問題になる誤判には二種類ある。
一つ目は、無罪になるべき者が有罪とされ死刑に処せられる場合である。
1980年代の4つの死刑再審無罪事件がその典型である。最近でも、無期懲役等の刑が確定した重大事件で、再審で無罪
になる事件、上訴審で有罪破棄無罪になる事件が相次いでいる。したがって、これらの死刑再審無罪事件は、戦後混乱期に
発生した過去の事件としては片付けられない。裁判は人為的な作業である。ミスは避けられない。刑事訴訟手続には、検察
官に対し合理的な疑いがない程度の証明を求める無罪推定の原則が存在するが、裁判実務において、合理的な疑いの有無の
境界は紙一重である。この原則が存在しても、誤判は必然的に発生する。上記再審無罪事件等の存在が示すとおりである。
二つ目は、無期又は有期懲役に処せられるべき者が死刑に処せられる場合である。量刑上の誤判である。
「永山基準」(永山事件の第1次上告審判決)が死刑のメルクマールかのように言われている。しかし、この判決には何
の「基準」も示されていない。死刑の量刑に当たり考慮すべき要素が列挙されているに過ぎない。結局のところ、そうした
事情の「総合考慮」によって死刑に処すべきかどうかが決まってくる。このことは、死刑にするかしないかの判断に「幅」
(いわば裁量)があるということを意味する。だからこそ、一審、控訴審、上告審で、死刑か無期かの判断が異なるという
事態が、頻繁に発生しているのである。
また、下級審の死刑判決に対し必要的上訴制度が取られていない現行法の下では、最高裁で、統一的な死刑・無期の量刑
判断がなされることは保障されていない。
結局のところ、量刑上、死刑になるべき事案だけが死刑になるということは、我が国の制度上保障されていない。無期に
なってもしかるべき事案で、死刑に処されることがあり得るということである。こうした量刑上の誤判も必然的に発生す
る。
確かに、誤判は刑事訴訟全体の問題であり、死刑制度固有の問題ではない。誤判を少なくするための刑事訴訟手続上の更
なる改善・改革は今後も進められていくであろう。しかしながら、裁判は人が為すものである以上、誤判も必然的に発生す
る。誤判により死刑判決に処せられ、死刑執行により命が奪われるということは絶対に避けなければならない。そのために
は、死刑制度を廃止するほかない。
6 死刑廃止後の最高刑(死刑の代替刑)
死刑を単に廃止しただけでは、現在の無期懲役が我が国の最高刑になる。無期受刑者仮釈放の実態を見ると、現行の無期
懲役刑については、仮釈放のない終身刑に近い運用がされてはいるが、法律上、受刑開始後10年経過すれば仮釈放が可能と
されている。現行の無期懲役が最高刑になるということになると、死刑廃止について、国民の理解をなかなか得られないで
あろう。死刑問題は人権に直結する問題であり、国民の多数決で決すべき問題ではない。しかし、我が国の刑事司法におい
て、長年続いてきた死刑制度を廃止するには、国民の理解をできるだけ得るよう努力することが求められる。
日弁連が、死刑の代替刑として、仮釈放のない終身刑(ただし、絶対的終身刑は非人道的刑罰であるという批判があるこ
となどから、刑執行後の事情により無期懲役への減刑を認める。)を導入することを提案しているのも、このような観点を
踏まえてのことであろう。
当会も、同様の観点から、日弁連の代替刑の提案を基本的に支持するものである。
代替刑の具体的な制度設計については、法制審議会において、自由権規約7条(何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若
しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けない。)及び10条(1項:自由を奪われたすべての者は、人道的にかつ人
間の固有の尊厳を尊重して、取り扱われる。3項:行刑の制度は、被拘禁者の矯正及び社会復帰を基本的な目的とする処遇
を含む。)の趣旨に加え、矯正の現場の実情・意見をも踏まえつつ、議論が尽くされるべきである。
7 犯罪被害者支援の抜本的拡充
犯罪被害者等基本法が成立したのが2004年である。そのころから被害者支援のための施策が創設・整備されてきた。公
判への被害者参加制度が認められるなど、捜査・刑事裁判に被害者が直接関連する場面での権利保障や支援は進んできた。
しかし、被害者の日常生活面における援助、刑事裁判終了後の援助、犯罪により受けた損害に関する賠償・補償を受ける権
利などについては、まだまだ不十分である。
日弁連は、2003年に「犯罪被害者の権利の確立とその総合的支援を求める決議」、2017年には「犯罪被害者の誰もが等
しく充実した支援を受けられる社会の実現を目指す決議」を採択し、被害者支援の拡充を求めてきた。当会においても、沖
縄県内には、犯罪被害者等に対する具体的な支援策を定めた条例は制定されていないことから、2021年3月「沖縄県及び県
内の各市町村において犯罪被害者等支援条例の制定を求める会長声明」を発出し、沖縄県及び県内各市町村に早急なる犯罪
被害者支援のための条例制定を求めた。
死刑制度廃止を議論するうえでは、被害者や遺族、ひいては国民の理解を得る必要があり、死刑制度廃止に併せて、犯罪
被害者支援を抜本的に拡充することが不可欠である。国及び地方公共団体に対し被害者支援の拡充を求めるとともに、当会
は、今後も犯罪被害者支援拡充のための活動を積極的に推進していく所存である。
8 終わりに
国際社会が死刑廃止に向かっているからといって、我が国がやみくもにそれに追随しなければならないということにはな
らない。しかし、死刑廃止に向かう国際的潮流の背景には、人間の尊厳及び基本的人権の尊重の重要性に対する認識の深
化、生命(権)の絶対不可侵性という理念・価値観の普遍化がある。我が国が、国際社会の中で、自由・民主主義国家のリ
ーダーとして発言力を確保していくためには、このような人権を巡る国際的動向を軽視することはできない。政府が本決議
を真摯に受け止め、死刑制度廃止に向けた作業に着手することを強く期待するものである。
当会としては、これまで以上に、死刑問題についての情報発信を始めとした死刑廃止に向けた活動、犯罪被害者支援のた
めの活動に取り組んでいく決意である。
2022年(令和4年)3月11日
沖 縄 弁 護 士 会